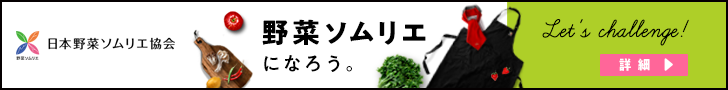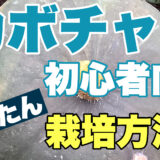初心者でもコツをつかめば大きく連なったサツマイモを育てることができます。
サツマイモは暑さに強く、チッ素分が少ない栄養分の少ない土壌でも育てやすいので
野菜づくりの初心者にもおすすめです。
他の野菜と違い連作障害が起きにくい点も育てやすさの理由です。
この記事は初めて家庭菜園でサツマイモを栽培する初心者の人に
苗を植えつけてから収穫できるまでの一連の流れの中で
- 栽培前に揃えたい道具・資材・肥料
- 収穫までの作業の一連の流れと作業手順
- 栽培を始める前に押さえておきたいポイント
が理解でき、スムーズに作業ができるようになります。
野菜づくりで失敗した後に事前に勉強しておけばよかったという後悔はよくあります。
失敗を繰り返して学んだ筆者のノウハウをお伝えしますのでぜひ参考にしてください

私は貸し農園で野菜づくりを始めて9年になります。
年間を通じて40種類の野菜を栽培しています。

目次

サツマイモの栽培に必要な道具や資材、肥料を揃えます。
【サツマイモ栽培に必要な道具】
まずはサツマイモ栽培に最低限用意したい道具を紹介します。
- 長靴
- 作業用手袋(軍手)
- 丸型ショベル
- 平鍬(ひらくわ)
- 丸パイプ
- じょうろ
- わりばし ※サツマイモの苗を植えつける際に使用します
【サツマイモ栽培に必要な資材】
- 黒マルチシート
- 穴あけ器

黒マルチシートを使ってマルチングすることで、土壌の乾燥防止、雑草の抑制、
土壌内の地温を高めることで生長を促す効果があります。
【サツマイモ栽培に必要な肥料】
- 苦土石灰
- 完熟牛糞堆肥(牛フン堆肥)
- 草木灰

鶏糞(けいふん)や化成肥料などの肥料を入れるとつるボケになりやすいので、
私は入れないようにしています。
【あると便利な道具&資材】
必須ではありませんが使用すると良い道具と資材の紹介です。
- 土壌酸度計(土壌の酸度を計測する道具)

土の酸度を測定して適性内に調整することで「生理障害」
を予防する効果があります。
栄養分や温度の過不足が要因で枯れたり、成長が鈍化すること。
高酸度によるアルカリ成分不足や同科目野菜の連作による栄養の過不足に注意が必要です

サツマイモ栽培の特徴を紹介します。
| 項目 | 特徴 |
| 栽培期間 | 植えつけ:5月上旬〜6月上旬 収穫:10月上旬〜11月上旬 |
| 育苗方法 | 苗(種イモから苗を育てることは可能だが初心者は苗の購入がオススメ) |
| 発芽地温 | ー |
| 育生適温 | 25〜30℃ |
| 好適土壌酸度 | 5.5〜6.0ph |
| うねの幅 | 90cm |
| 株間 | 30cm |
| 連作障害有無 | 連作障害無 |
※栽培期間は目安です。地域や品種により異なリます。

サツマイモは梅雨時期の雨で成長が活発になるので、
梅雨前には苗を植え根づかせておきましょう。
サツマイモの栽培の流れを紹介します。
苗を植え付けてから約110~120日前後で収穫できます。
・長さが15〜20cm、節の間延びがなく4〜5節あり、
葉の色が濃く茎がしっかり太い苗を選ぶ
・良い苗選びはサツマイモ栽培成功のポイント
・購入後すぐに植えつけず、苗を少ししおれさせる。新聞紙で包み湿らして保存するとよい。
安納芋の苗は他の苗と比較して小ぶりになります。
・植えつけ2週間前には土を耕しておく
・土壌酸度計を使用し酸度を測定する(ph5.5〜6.0が最適)
・酸性土壌(5.5以下)の場合、苦土石灰をまき酸度を調整する
・1週間前に、牛糞堆肥(ぎゅうふんたいひ)・草木灰を入れて耕す
「石灰」や「草木灰」のカリウム成分を与えるとサツマイモの甘さが増すと言われています。
・深く耕し、水はけをよくする為にうねは高め(25cm以上)にたてる
・うねを立てた後は黒マルチシートでマルチングをおこなう。
乾燥防止、雑草の抑制、土壌の地温を高める効果がある。
平鍬(ひらくわ)、丸型ショベル、丸パイプ
苦土石灰、完熟牛糞堆肥、草木灰、鶏糞(けいふん)肥料 ※少なめにする
※酸度計は必要に応じて使用する
※苗3つ分
苦土石灰・・・100g(3握り分)
完熟牛糞・・・2kg(5リットルバケツ一杯分)
草木灰・・・ 100g
鶏糞肥料・・・ひと握り程度(少しでよい)
・サツマイモの苗を挿す
黒マルチシートに穴あけ器で30cm間隔に穴をあける
・穴あけ器で開けた穴に割り箸で10cm程度土壌に突き刺し、穴に苗を挿す
※節3つ分くらい土中に埋まるように挿す(斜め植え)
・苗を植えた後はジョウロでしっかりと水を与える
・植えつけから1週間は毎日水やりをおこない定植(根を張らせる)させる
‘

植えつけから1週間水やりを行い定植させるのが理想ですが、私のように毎日水やりはできない場合はうねの間にバケツで水を流し込んで水たまりにしておくとうねの乾燥を防げるのでおススメです。(雨が多そうな週に苗を植えるのもいいですね)
【苗の植えつけ方法と特徴】

| 植えつけ方法 | 特徴&メリット |
| 水平植え | 一般的な方法、イモの数が増える |
| 斜め植え | 苗を定植させやすい |
| 垂直植え | イモが大きく甘く育つ(数は少ない) |

苗を植える株間や埋める節数を変えると収穫できる芋の数や大きさが変わります。
節数を増やすと芋の数が増え、株間を広げると大きなイモが収穫できます
ジョウロ、穴あけ器、割り箸
・ツルが伸びていくと伸びたツルから土中に新しく根を生やします。
根が張ると栄養が分散するので、ツルを持ち上げ根を引き剥がしてツルをうねの中央に寄せておく
・ツルが伸び根を張り始めたなと思ったら定期的に実施する。


栄養分を分散させずに株元に集中させイモをしっかり実つかせます。
・葉の色が黄変してきたり、枯れてきたタイミングが収穫のサイン
・収穫の判断がつきにくい場合は「試し掘り」をしてみると良い
・収穫できるようであれば株元のツルを切り取り1週間ほどおき土の中で追熟させる
・収穫は晴れた日の午前中におこないます。
※掘り起こしたイモは半日畑でそのままにして乾燥させる
その後、ダンボールなどに入れて日の当たらない場所で保管する
※雨などで土がドロドロの状態で収穫すると収穫した芋が腐りやすくなります
・イモの掘り起こす方法は、先に伸びたツルを株元で切り取ります。
・黒マルチシートを剥がしながら株の周辺からショベルで少しづつ掘り起こす
※低温に当たると芋が腐るので、霜が降りる前には収穫してしまう[/tl]


よく店頭で見られる代表的なサツマイモの品種をまとめました。
一般的な品種は、苗がしっかりして育てやすい「鳴門金時」や「紅あずま」の品種です。
最近の傾向として糖度の高いブランド芋の苗が出回っており「安納芋」や「シルクスイート」の
品種も人気です。
| おすすめ品種 | 特徴 |
| 鳴門金時 | ホクホク、生育が早く、収穫量が多い 初心者向き |
| 紅あずま | ホクホク、生育が早く、貯蔵性が良い 初心者向き |
| 安納芋 | ねっとり、焼き芋やスィートポテト向き |
| 紅はるか | しっとり、収穫の形がよく焼き芋や蒸し芋向き。後味が良いのも特徴 |
| シルクスイート | ねっとり、焼き芋やスィートポテト向き |
サツマイモによくみられる病気
サツマイモ栽培でみられる主な病気をまとめました。土壌内の菌が原因での感染が目立ちます。
収穫量に影響するだけではなく、他の株にも伝染する病気もあるので注意が必要です。
| 病気名 | 特徴 |
| 立ち枯れ病 | 下葉が黄変してしおれ始める。症状が進行してしまうと株全体が枯れてしまう。 |
| つる割れ病 | 土壌の菌及び種イモから発症し下葉がしおれ始める。日中は元気だが元に戻るを繰り返し、やがて茎が割れてカビ発生要因になり株全体が枯れる。 |
| 黒斑病 | 土壌の菌が原因で発症し、イモや葉に被害が出ます。初めは黒褐色の病斑ができ、やがて進行するにつれ黒さが広がります。表面がくぼんだ円形となって中央部にカビを生じる。 |
| 斑紋モザイク病 | アブラムシを介して発症する病気で症状として葉に紫の斑点が広がる。影響として芋の生長不良につながり収穫時に芋の表面が全体的に色褪せや奇形の芋になる。 |
| かいよう病 | 降雨の水の流れで病原体が広がり気孔や切り口から体内に侵入し発症する。葉・茎・芋に病班が現れる。発症すると他の株にも伝染し被害を拡大させるとともに進行すると葉や茎を枯らしてしまい収穫量に影響する。 |

病気がみつかった場合は他の株に広まる前に抜いてしまいましょう。
サツマイモによくみられる害虫
サツマイモによくみられる害虫の種類と被害をまとめました。
土壌内に潜伏する虫が多く土を掘り起こさないとわからないので注意が必要です。
| 病気名 | 特徴 |
| ネキリムシ | 夜間に地表へ出て地際の茎を食害する。昼間は土の中に潜伏しているので退治しにくい。 |
| ヨトウムシ | ネキリムシ同様、夜間に地表へ出て地際の茎を食害する。昼間は土の中に潜伏し退治しにくい。 |
| アブラムシ | 繁殖力が強くウイルス病を媒介し被害を広める |
| ハリガネムシ | 芋に針金が貫通したような痕を残す。そのままにすると食害が広がり、芋が穴ボコだらけに。 |
| ネコブセンチュウ | 根に穴をあけ中に寄生するとしおれて枯れてしまう。 |
| アカビロードコガネ | コガネムシの幼虫で土壌内でイモを食害する |

生長過程で害虫に茎や葉を食害されるとサツマイモの収穫量に影響します
①赤しそ
・赤い葉が嫌いなアカビロードコガネなどの害虫よけになります。
②つるなし品種のマメ科野菜(つるなしインゲン)
・サツマイモのツルに守られカメムシなどの害虫よけになります。
①購入した苗はすぐに畑に植えつけない
購入した苗は1週間ほど自宅で保管し苗を乾燥させしおれさせる。
その理由として、
- 苗の切り口を乾燥させ切り口からの病気感染を予防する
- 乾燥気味にさせることで茎から新しい根を生やしやすくする
購入してすぐの苗は鮮度を保つために親ツルから切り離して間もないものが多く、
そのまま植えつけると傷口から感染する恐れがあります。
購入した苗は湿らせた新聞紙に包み乾燥気味に保管します。
水分が少なくなるので葉はしおれますが新しい根が出てきます。
新しい根が出た状態で植えつけると定植しやすくなるのでオススメです。
②肥料は最低限に、株元に養分を集中させる
良質なサツマイモを収穫するためには株元の根に栄養を集中させることが大切。
葉や茎が勢いよく育ったが意外と収穫できた芋が少なく小さかったというのはよくあることです。
その失敗要因として、
- 葉と茎(つる)に栄養分を取られイモに栄養がまわらない「つるボケ」を起こしている
- 勢いよく伸びたつるをそのままにすると伸びたつるから新しい根が生え栄養分を取られる
つるボケにならないためには、土づくりの際の元肥(鶏糞や化成肥料)を控えめにする。
私は初めの元肥は入れないようにしています。鶏糞(けいふん)などの肥料に含まれるチッ素分が
多いと栄養が葉やつるを伸ばすことに栄養がとられてしまい、
肝心のイモにいく栄養分が少なくなります。
結果肝心のイモが大きくならなかったり、甘くならなかったりします。
さらにつるが伸びると土壌との接地点で新しい根が出てきます。つるボケ同様そのままにしておくと
根をどんどん生やしてしまい栄養分を分散させることになります。
つるが伸びた時は定期的に「つる返し」をおこなうことが必要です。
葉やつるに栄養分を分散させることなくイモに栄養分を集中させることで
良質のイモが収穫できるようにしましょう。
③美味しい芋を収穫するためのコツ
大きさや形の良い美味しいサツマイモを収穫するためにはコツを紹介します。
- 苗の植えつけの際に赤しそを混植する
- 収穫時先につるを切り1週間ほどしてから掘り起こす
- 掘り起こしたイモを1週間天干しさせ追熟させる

サツマイモの株間(30cmの間)コンパニオンプランツとして「赤しそ」を植えると効果的です。
肥料分をよく吸収する赤しそを混植すると、土の中のチッ素分が適度に奪われて、
サツマイモはつるぼけを起こさずに、葉や茎で作られた養分がイモに行き渡ります。
混植することで相乗効果を発揮する植物(野菜)をコンパニオンプランツといいます。
収穫時には1週間前につるを刈り取ってそのままにしておき、養分をイモに転流させると
美味しいイモが収穫できます。
また、収穫したサツマイモは掘ったあとすぐに食べるより、
1週間ほど置いておき追熟させるとデンプンが糖化することより甘くなるのでオススメです。
また、サツマイモの保存は直接日が当たらない風通しが良い場所で保管するようにしましょう。
それではサツマイモの栽培方法のまとめです。
- 栽培に必要な道具や資材、肥料を揃える
サツマイモの栽培は基本的な道具や資材を揃えれば栽培できます。
うねには土壌の乾燥防止、雑草の抑制、土壌内の地温を高める効果を得るために
黒マルチシートでマルチングするのがオススメです。
元肥は控えめにします。ただ、サツマイモの甘さが増す草木灰を入れると良い。
- 一連の作業の流れと作業手順を把握する
サツマイモの一連の作業の流れを把握した上で作業を進めましょう。
サツマイモの収穫までの作業の流れはカンタンです。苗を定植させた後は
ほとんどほったらかしでも育ちます。
梅雨に入るまでに苗を定植させ一気にツルを成長させ、伸びたツルが土壌に
新しく根を張らせないように定期的に「ツル返し」するだけで大丈夫です。
また、甘く美味しいイモを収穫するために収穫前1週間、土中で追熟させ
収穫後さらに1週間追熟させるとより甘さが増し美味しく頂けます。
またサツマイモの保存方法は直接陽が当たらない暗所で保存します(冷蔵庫で保存はしない)
- サツマイモ栽培のトラブル・病害虫対策
サツマイモの病気やトラブルは多雨による生理障害や土壌内の病原体や害虫の被害によるものが多い。
多雨による生理障害の被害を受けないよう、うねは高めにする、窒素分の過多による栄養障害
を受けないようにコンパニオンプランツとして赤しそを混植すると効果的。
- 栽培で気をつけたい3つのポイント
サツマイモ栽培で気をつけたいポイントは、病害の被害を受けないよう購入した苗をすぐに挿す
のではなく、つるの切り口を乾燥させてから植えつける。
つるボケにならないよう元肥は少なめにする。
また、ツルが伸び新しい根を張らせないために定期的につる返しをおこなう。
甘いイモを収穫するために土中、収穫後の2週間追熟させます。
サツマイモの苗の植えつけから収穫までの栽培の流れと栽培方法を理解いただけたでしょうか?
この記事がサツマイモを栽培するために少しでもお役に立てれば嬉しいです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。